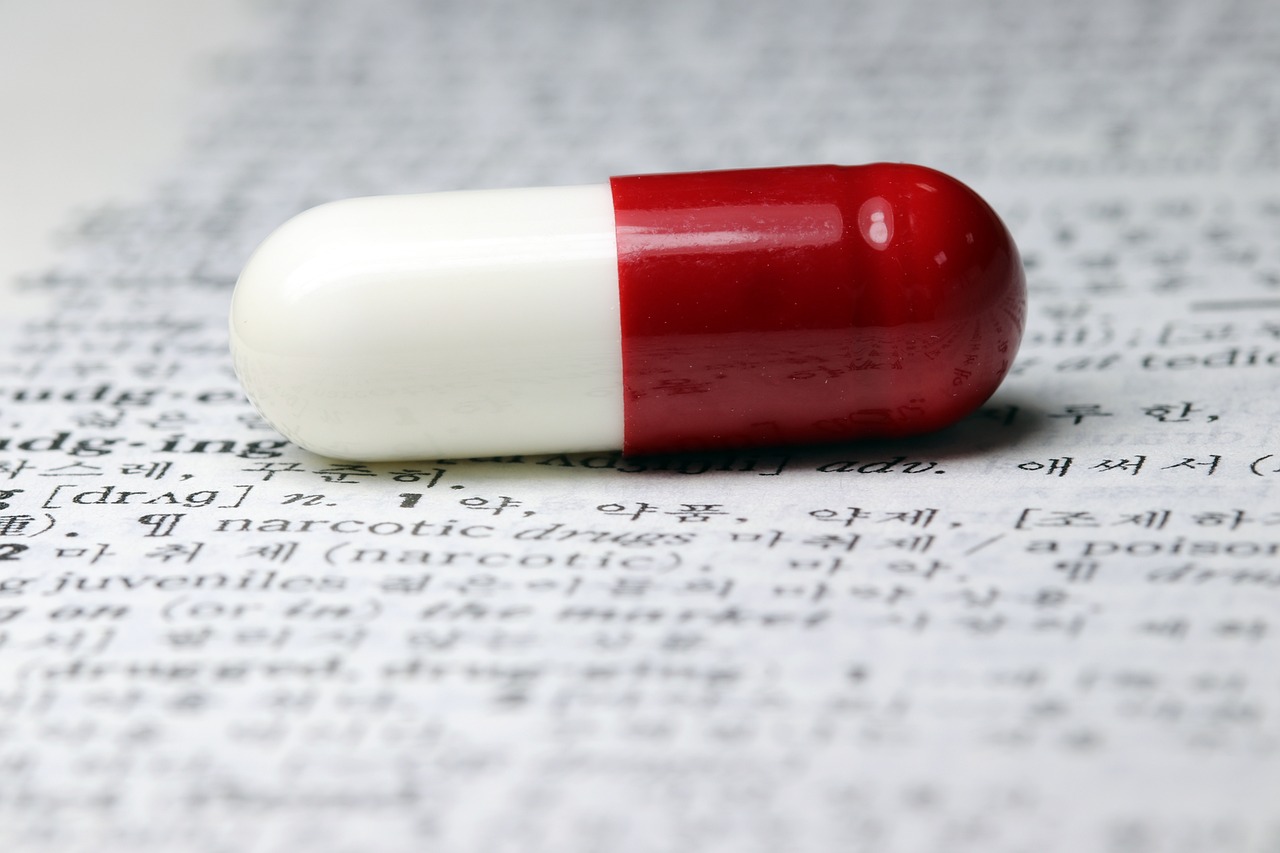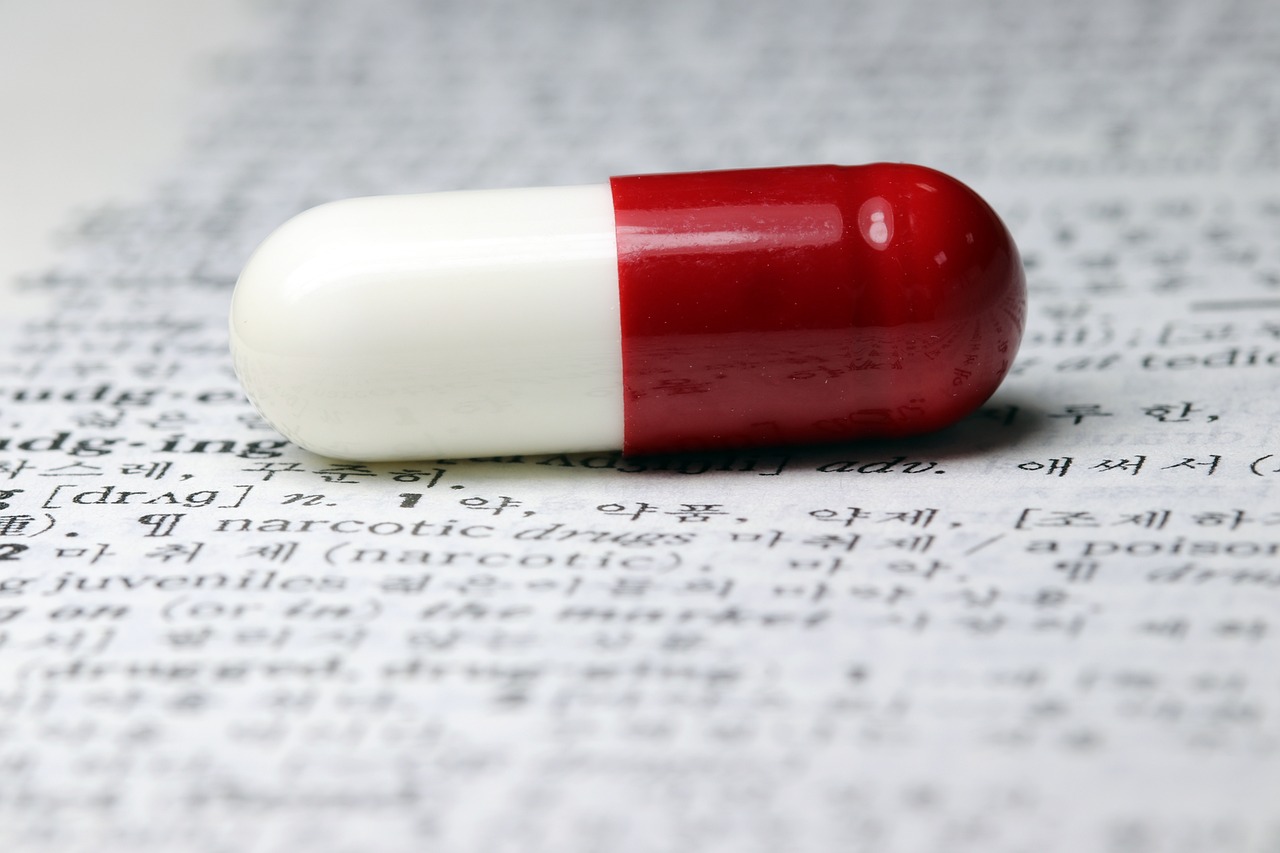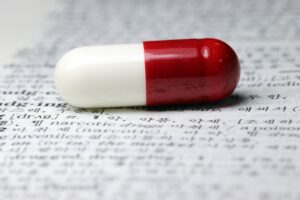先日、友人から
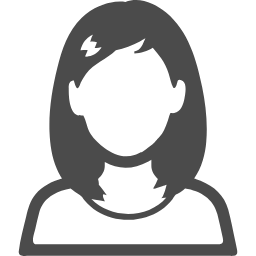 薬剤師
薬剤師病院と調剤で仕事は違う?
と質問されました。
転職する前の私は、病院での勤務経験が10年以上あるので、調剤薬局でもやっていけるだろうと甘くみていました。
しかし、転職後に勘違いだったと痛感させられます。
調剤薬局では、病院で培ってきた知識とはまた別のノウハウや知識が必要なのです。
本記事では、病院と調剤の経験をもとに、薬剤師の仕事内容についてお伝えいたします。
この記事を読むことで、病院と調剤で働く薬剤師が何を考え、どのような仕事をしているのかを理解できるはずです。


病院薬剤師と調剤薬局の薬剤師では、目指すものに違いがある
病院薬剤師は医療の質向上に専念できる
病院薬剤師と調剤薬局の薬剤師は業務内容が大きく異なります。
例えば、私が勤めていたDPC病院では、医療事務課が保険査定への対応をしてくれていたので、薬剤師の業務には含まれていませんでした。
そのため病院薬剤師は、患者さん個々の医療の質向上に専念できていました。
また、注射剤の投薬や入院患者への対応、看護師への薬剤説明など医療体制の効率化などが院内薬剤師の主な業務といえます。
  | 基礎から読み解くDPC第3版 実践的に活用するために [ 松田晋哉 ] 価格:3740円 |
  | 【送料無料】 DPCによる戦略的病院経営 急性期病院に求められるDPC活用術 医療経営士テキスト 上級 / 松田晋哉 【本】 価格:3300円 |
  | DPC点数早見表 2022年4月版 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 [ 医学通信社 ] 価格:4950円 |
調剤薬局の管理薬剤師はコスト意識が必要
一方、調剤薬局の管理薬剤師はもっと経営者寄りの考え方が必要です。
調剤薬局では、管理を含む薬剤師+医療事務という少人数体制でオペレーションをしています。
管理ではない勤務薬剤師として働く場合でも、経営者の観点を持つことで社長や管理薬剤師等と意思疎通がしやすくなるので、経営の基礎知識を持っておく方がよいでしょう。
患者さんが持参した処方箋チェックし処方するだけでなく、在庫チェックや発注、機材管理、患者さん待ち時間管理、そして何より保険で査定されないための対応が主な業務となります。



管理薬剤師やらなければいけないことが盛りだくさんなのです
病院薬剤師と調剤薬局の薬剤師が意識していること
病院では、エビデンスベースに処方が成されているか一般常識に照らし合わせて確認します。
一方、調剤薬局では、添付文書に忠実に確認します。
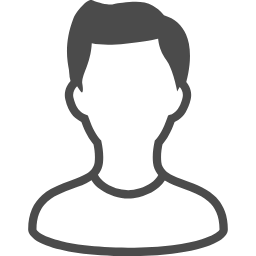
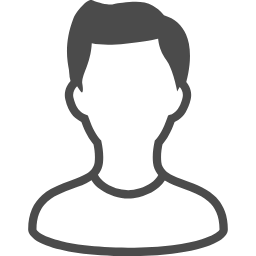
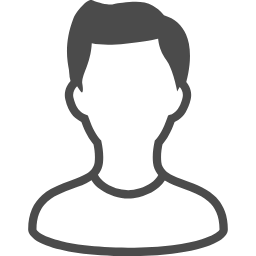
似たような仕事なんじゃないの?
と言われてしまいそうですが、重視する部分が異なるのです。
病院では、分業体制により医事課が保険査定の対応をしてくれているため、病院薬剤部は添付文書だけでなく、ガイドラインや臨床試験等のエビデンスをベースとした確認に集中できます。
添付文書に書かれていない内容でも、最新のガイドラインや臨床試験に処方の根拠がないかを深堀りしていくイメージです。
一方調剤薬局では病院とは異なる経営母体なので、保険査定を受けてしまえば利益逸失に直結してしまいます。
医療事務担当者が少ないので、すべてを丸投げすることはできず管理薬剤師が率先して確認する必要があります。
ここで確認することは、添付文書通りに処方が成されているか否かです。
クリニックから処方されてくる処方箋には、添付文書から逸脱した内容も意外に多いものです。
例えば、漢方薬の処方で『食前や食間』ではなく『食後』で処方されていても、病院では服薬コンプライアンス向上のためだろうと疑義照会をしていなかったのですが、調剤薬局では医師に疑義紹介して確認をしておかないと保険査定で切られてしまう可能性があります。
また、一般名処方に対してジェネリックでお渡しするケース、規格が違うジェネリックを使用するときなど、様々なパターンで原則処方医師の確認が必要になります。
門前ガチャ?医師の方針で苦労することも
調剤薬局あるあるとして、想像以上に門前クリニックとの関係が濃密です。
医師にもいろいろな方がおられますが、
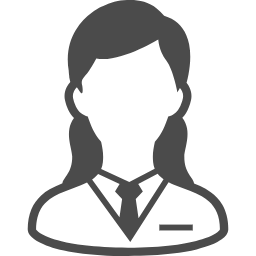
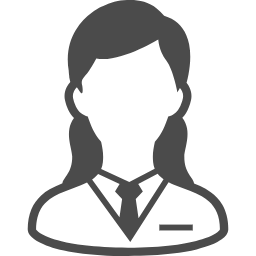
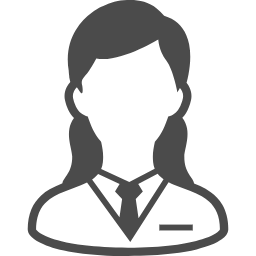
これは○○で良かったでしょうか?



そのままの処方でいいよ
こんなやり取りを何度も繰り返すので、門前クリニックのDrと相性が合わないとかなりしんどいです。
病院では一般常識の範囲内で医師への疑義紹介をしていましたが、調剤薬局ではそうはいきません。
クリニックとの関係が濃密すぎて、門前の医師の治療方針・指導内容からズレないように患者指導をしなければなりません。
そうしないと、
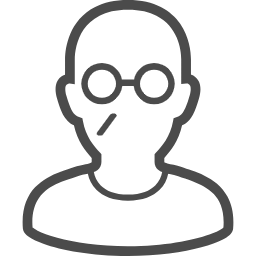
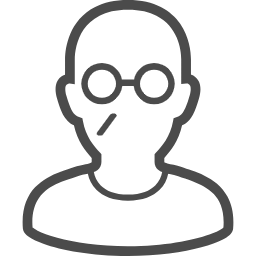
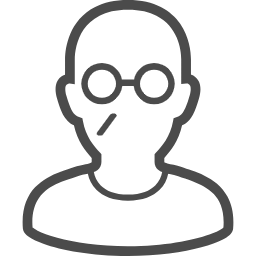
医師は○○と言ってたのに、あそこの薬剤師からは△△と言われたんだが…
と、患者を惑わす事になってしまい、医師との関係性にも亀裂が入ってしまいかねません。
添付文書通りでない場合に保険査定のリスクがあれば疑義紹介をしますが、できる限り医師との関係性を悪くしたくないので細心の注意を払っています。
調剤薬局の薬剤師はタイムマネジメントが大切
病院薬剤師の時は、患者への服薬指導は理解しもらえるまで時間を掛けていました。患者も入院していることもあり、比較的聞く耳を持ってくれているケースが多いので残業等で対応していました。
しかし、調剤薬局ではそうはいきません。
1人に対応する時間をかければかけるほど、他患者の待ち時間がどんどん長くなってしまいます。
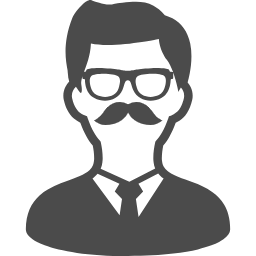
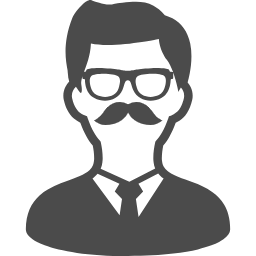
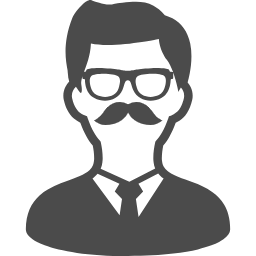
病院でも待たされた挙句、薬局でもまた待たすのか!
と声を荒げる患者もいます。
薬剤師の処方箋取り扱い枚数は40枚/日が上限とされており、その人数を元に各店舗の薬剤師の人数が決められています。そのため、その人数で患者個々のニーズに応じた服薬指導をしていきます。
調剤薬局に転職した当初は、より良い説明をすることに重点を置いていたのですが、そうすると患者一人あたりの説明時間が長くなりがちです。
しかし現実は、ご自身の状態を話したがらない患者や、詳しい指導を望んでいない人の方が大半です。
患者個々のニーズを瞬時に聞き取るスキルや、それに沿ったコミュニケーションと服薬指導を身に着け、なんとか薬局の混み具合とのバランスがとれるようになっていきました。
病院薬剤師と調剤薬局薬剤師にとって大切なのは患者ニーズの把握
病院に入院してくる患者は、今まさに自分の健康や病気に向き合っているタイミングなので、ご自身の状態を把握しようとする意識が強く、薬剤師の指導もしっかりと聞いてくれます。
ですが、調剤薬局に来られる方は処方された薬さえ飲んでいれば、日常生活に支障がない方もたくさんいて、
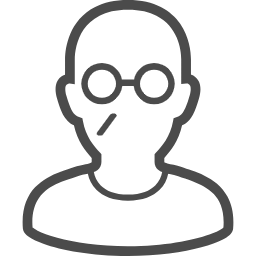
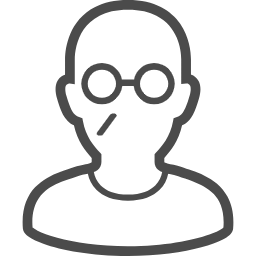
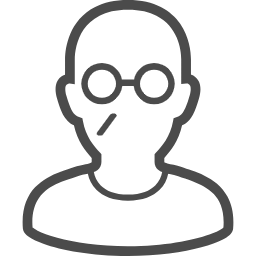
薬を貰うためだけに、なんで薬剤師に根掘り葉掘り検査値などを聞かれなければならないんだ!



薬剤師は医者が処方した薬を間違わずに渡すだけでいいんだ!!
という患者の方が多いです。
それでも真摯に対応し続けることで、信頼関係が構築できることもあります。(疎まれている状態から患者に心を開いてもらうには、それなりの誠意と期間が必要ですが…)
調剤薬局では、接客業としてのマインドやコミュニケーションスキルが必要不可欠である、といえるかもしれません。
勤務時間と給与等の比較
病院時代の方が、残業をしていた時間は圧倒的に多かったと思います。
基本的な業務時間は9時~17時半でしたが、21時超えの残業もしばしばありました。



私が自己研鑽として行っていただけですが…
今働いている調剤薬局の業務時間は9時〜18時で、残業は少なくほとんどが時間内にこなすことができています。
収入事情は、私がいた病院は薬学部がない地方だったので、都市部に比べると比較的待遇が良かったはずなのですが、福岡の調剤薬局の方が残業も少なく給料が高いイメージです。
調剤薬局は季節的な繁閑の差が大きく、繁忙期は休み時間が十分にとれない時もありますので、人によって合う合わないがありそうです。
勤務時間と収入だけでみると、



病院よりも調剤薬局に軍配が上がります
という感じですね。
病院 or 調剤 で転職に悩まれている方へ



病院薬剤師と調剤薬局、どっちがいいかな?
と悩む学生は沢山います。
私は病院と調剤の両方を経験しているので、病院内での患者さんの治療内容や不安などを具体的にイメージできます。
例えば、患者が手術歴があると教えてくれた時に、その患者がどんな病状だったのか、何が原因でその病気が引き起こされたのか、などが自然に頭に浮かぶのです。
それは病院勤務時代にそういった患者の経過をずっと側で見て、経験してきたからこそだと思います。
例えば大動脈解離という病態の治療法だけではなく、実際にその患者がどれだけ痛い思いをしたのか、なぜそのような事態に陥ってしまったのか、治療後はどんな事に気をつけて生活していかなければならないのか、など。
それらの事を踏まえて高血圧症だけの患者と、大動脈解離の手術歴がある高血圧症の患者とでは、後者では指導方法の方法も大きく変わります。
病院薬剤師時代は拘束時間的にも、お給料面でも調剤薬局とは待遇が良いとは言えませんが、調剤薬局だけでは経験することのできない病態を側でみて経験し、そこから回復していく患者のサポートができた事は私にとってはかけがえのない宝物です。
もし、収入や勤務時間だけで病院薬剤師の選択肢を狭めているのであれば、薬剤のやりがいや経験を積めるなどを指標に加えてみてください。



薬剤師としての経験を積みたい!やりがいを感じたい!
方には病院薬剤師はとてもおススメですよ♪
ここまで読んでいただいてありがとうございました。引き続き薬剤師の視点で情報発信を続けていきますので、今後ともよろしくお願いします。