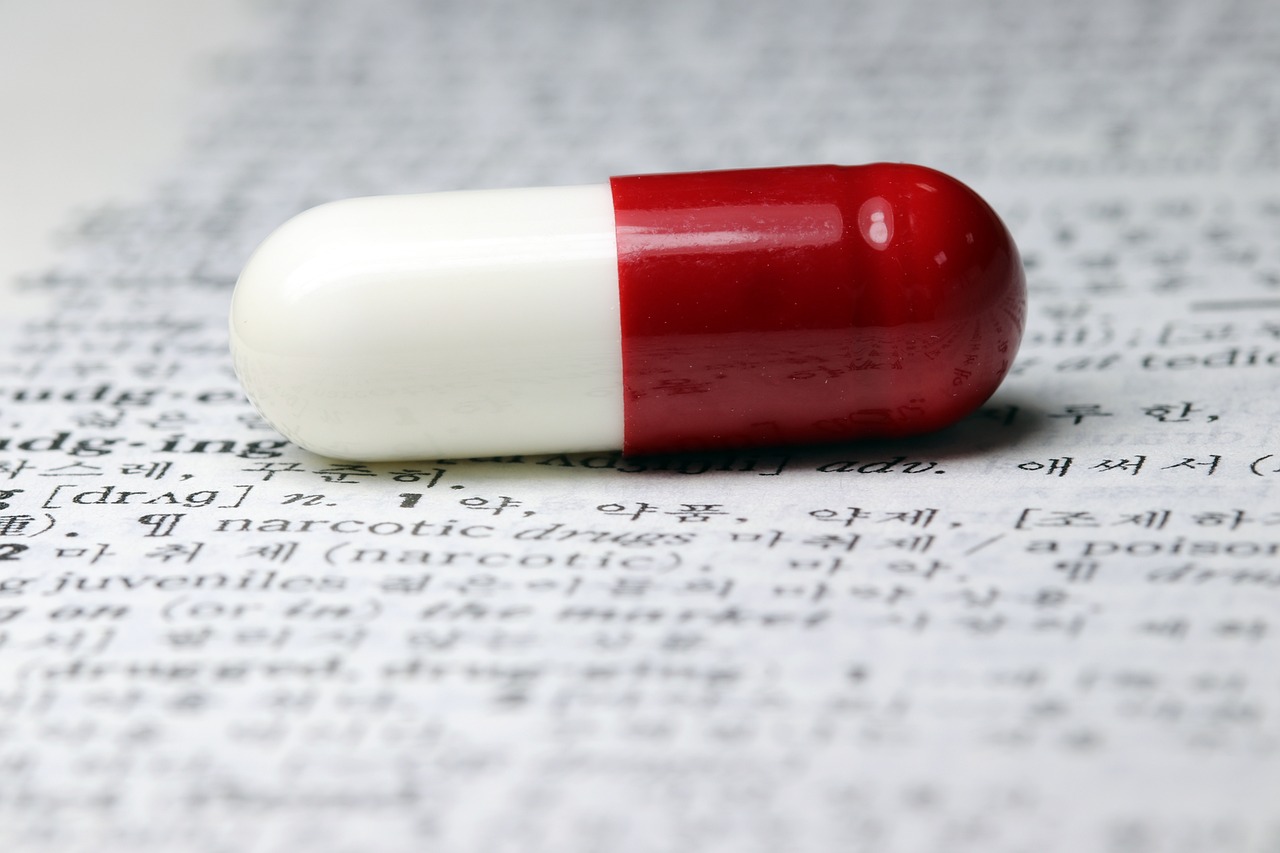病院薬剤師の仕事はどんなものがあると思いますか?
私は病院薬剤師として10年以上勤務してきましたが、想像以上に業務が幅広いです。
この記事を読むことで、病院の薬剤師業務に興味を持たれている方が、より具体的にイメージをしていただくこと出来るようになるはずです。

病院薬剤師の仕事で大変だったこと
病院薬剤師の主な仕事として、処方箋の調剤、監査業務、入院患者さんへの服薬指導などが挙げられます。
その他にも、患者さんの採血データや他の投与されている薬剤の確認、医師の処方内容が正しいか処方箋の一枚一枚の精査し問題があると疑義照会、抗がん剤の調製や院内製剤の調剤など多岐にわたります。
特に大変な仕事が、医師や看護師からくるたくさんの問い合わせ対応です。
例えば、
 Dr
Dr「患者に○○を投与したいんだけど、この患者の状態だとどれくらいの投与量にすればいい?」
などが来るのですが、若手の頃は医師のもごもご話す声が聞き取れませんでした。名前も名乗らずに一方的に喋って電話を切られることもありました。
精一杯聞き取れた内容を様々な仮説を立てながら読み解き、先輩や同僚に相談し、調べて折り返しの電話をします。
そうやって必死に調べても、、



返答が遅い!!伝えた意図と全然違うし
と叱責されたこともありました。
それでも少しづつ、喋り声だけでどの医師からの指示か判断できるようになり、質問へもすぐに回答できるようなスキルが身に付いていきました。
さらに経験を重ねて中堅の立場になってくると、より高度な回答が求められるようになっていきます。



◎◎の感染症の患者なんだけど、耐性菌ができてるんだよね。
他になんかいい抗生剤ある?投与量の目安も教えて



〇〇さんに合う中心静脈栄養のメニューを教えて
正確に回答するにはガイドラインや参考書だけでは難しく、メーカーに問い合わせたり、文献で対応できるものや、どれだけ調べても回答できないものなど様々です。
さらに、看護師からもたくさん問い合わせが来ます。



ルートが1本しかとれない患者に○と×と▽と△と●と◎を投与しないといけないのですが、配合変化はないですか?



注射剤の〇と△の配合変化の試験データはあったとしても、○と×と▽と△と●と◎全てを網羅するデータはありませんか?
注射剤の配合変化については、ほとんど試験データがありません。
配合変化が起こりうる可能性が少しでもあるのであれば、別ルートをとってもらう、又は側管から入れてもらう、など様々な方法を検討する必要があります。
病院薬剤師に向いている人は自己研鑽を欠かさない!
病院薬剤師は、医療スタッフからの質問に対応できるスキルが必要不可欠です。
新たな治療法が発見され、根本から覆されることもしばしばです。常々知識をアップデートしなければならず、自己研鑽に終わりはありません。
思い返すと自分の無力さを痛感し続けた日々でした。
しかし、一日一日の仕事をこなしていったことで、いつの間にか循環器領域の専門薬剤師としての土台を築くことが出来ました。
病棟での薬剤師業務は成長への近道!
私が若手の時代に、病棟専任薬剤師制度が始まりました。
病棟専任薬剤師は、ナースステーションに常駐し看護師などからの質問対応、入院患者の薬剤管理、向精神薬の取り扱い確認などを行います。
また、定期的に看護師への薬剤勉強会や患者教育の勉強会なども行います。
私が勤めていた頃の病院は、看護師と薬剤師は犬猿の仲だったのですが、この制度が始まったことで日々の業務や自己研鑽が少しずつ認められ看護師との距離が縮まり、次第に意見交換ができるようになっていきました。
また、医師が病棟を訪れた際に情報交換をする時間も増え、薬剤師では判断できないことなどを質問するなど、医療の質向上とともに薬剤師として成長する機会も増えました。
その時の経験があったからこそ、今働いている調剤薬局では経験できない患者さんの病院内での動きや、心情の変化をイメージすることが出来ています。
その時の経験は今でも貴重な財産となっています。
病院薬剤師の仕事はやりがいの宝庫
病院薬剤師の仕事でやりがいを感じるのは、入院患者へ薬の説明をするときです。
入院を機に初めて薬と付き合っていかなければいけなくなった患者も多いです。きちんと薬の服用ができなかったが故に、病状が悪化し入院に至る人もいます。
そういった方々には、ご自身の病気にしっかりと向き合っていただき、きちんと薬を服用していただかなければなりません。
ご高齢の方は、ご自身では数多くの薬の管理が難しいケースがあります。そういった場合、患者家族を含めてご理解とご支援をいただけるように入念に相談をしていかなければなりません。
入院患者と接する回数が増えるにつれ、
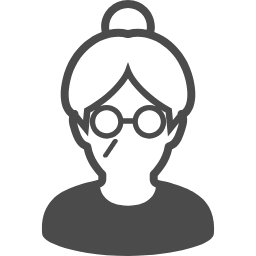
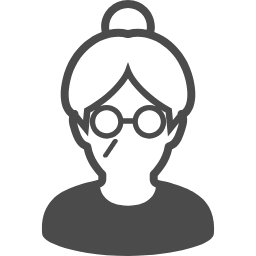
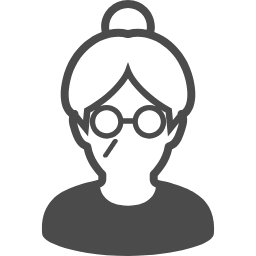
医者は愛想ないけど、あなたには相談しやすいねぇ
と打ち明けてくれる患者がいるなど、患者とのコミュニケーションにより信頼を感じるなどでやりがいを感じます。
また滅多にあることではありませんが、医師が気づいていない副作用に最初に気づくこともあります。
薬によっては重大な副作用を引き起こす場合もあります。確信が持てなくても、疑わしいのであれば報告しなければなりません。
確信が持てないことを医師に意見することは、それなりの勇気と覚悟がいります。
ですが、こんな私でも過去に何度も未然に報告することで予防できたという経験をしてきました。
正しく服用していれば起きなかった副作用や、誤った服用方法で病状が悪化するなどはあってはならないことです。
これらを防ぐことこそが薬剤師の存在意義だと考えています。
まがりなりにも自分の行動が患者の命を救えたことは、病院薬剤師の存在意義を実感したいい経験です。
【薬剤師の鑑別業務】持参薬多すぎ問題
病院薬剤師の業務で忘れてはならないのは持参薬の鑑別です。
DPC病院では、薬剤費抑制のため入院患者全員の持参薬を全て確認して報告書を作成しなければなりません。
患者の持参したお薬箱から一つ一つ取り出して、お薬手帳や薬情などの用法用量を確認します。
病院に採用されていない薬剤があれば、医師に代替薬の提案をしなければなりません。
その際は「今日の治療薬」を参考にして鑑別書を仕上げていました。
  | 価格:5280円 |
鑑別業務で大変なのが、一包化されている錠剤ならまだしも、原型のない粉砕された粉薬や混合された外用剤、サプリメントなど多種多様なものを確認することです。
患者によっては、何百錠もの飲み残しや使用期限が切れている薬剤を持ってくる人もいます。1錠ずつ切り刻まれているなど、数えるだけでも多くの時間を費やさなければなりません。
また、麻薬や睡眠剤を混ぜてしまっているケースもあるので要注意です。
それらは全て患者の持ち物なので、1錠たりとも紛失するわけにはいきません。
持参薬鑑別のときは針刺し事故に注意
以前、持参薬を確認しようとポーチを空けたときに、インスリン製剤の針が剥き出しになっており、同僚の指に刺さってしまいました。
患者がインスリン製剤の針を付けたままにしていたのです。しかも、その患者はB型肝炎を罹患していました。
これにより同僚は、B型肝炎への感染リスクを負ってしまったのです。
その後同僚は、定期的に採血をして数ヶ月間検査を行いました。幸いB型肝炎を発症しなかったので良かったのですが、薬剤師業務は様々な潜在リスクを負っていることを痛感しました。
その後、医療安全委員会や感染症対策委員会で協議し、より慎重に持参薬鑑別の業務に臨むようになりました。
一包化製剤の判別方法
入院患者の多くは内服が一包化されています。
一包化とは、錠剤がヒート包装から取り出され、1回に飲む薬剤毎にワンパック化されたもののことです。
通常、錠剤が入ったシートには○○錠△mgと書いてあるのでなんの薬か一目瞭然ですが、一包化されてしまうとシートの表示には頼れません。
世の中の錠剤には識別コードといって、一つずつ数字やアルファベットなどが書かれています。
私が所属していた病院の先輩薬剤師は、何千もの採用薬剤の識別コードを見ただけで、この薬が○○錠△mgであるかを暗記していました。
今でこそカタカナで薬剤名を印字してある薬も沢山出てきましたが、私が勤め始めた頃は本当にアルファベットと数字だけのシンプルなものか多かったので、分からない識別コードがある度に辞書で調べていました。
  | 価格:5280円 |
せっかく暗記していても、識別コードが変更になったり採用品が変わったりで、日々知識をアップデートしなければなりません。
一包化については基本的に機械が行いますが、機械が誤作動を起こす懸念もあります。見た目が似ている違った薬剤がセットされているかもしれません。
1錠1錠きちんと処方箋通りの薬剤が入っているか、識別コードを確認しながら監査をします。
これらの業務を時間内に処理していくことは思いのほか大変な作業なのです。
まとめ
これまでお伝えしてきたように、病院薬剤師の業務範囲は膨大です。
10年間病院内で働いてきた私でも、経験していない仕事が沢山ありますし、日々の仕事をこなしていくだけでも大変でした。
しかし病院で働いてきたからこそ、専門だった循環器領域では医師に何度も提言してきた経験があるし、関連領域で幅広い知識を身に着けてきたことが大いなる自信になっています。
これらは、私の薬剤師としてのキャリアの土台となり、今の調剤業務にも役立っています。
病院は、薬剤師として深い経験を積み、一人前に成長したいと考えている人にとって、全力でおススメできる職場です。
ここまで記事を読んでいただいてありがとうございました。
薬剤師の仕事に興味を持っていただける方がもっともっと増えるよう、これからも経験してきた薬剤師の仕事内容を発信していきますので、応援のほどよろしくお願いします。