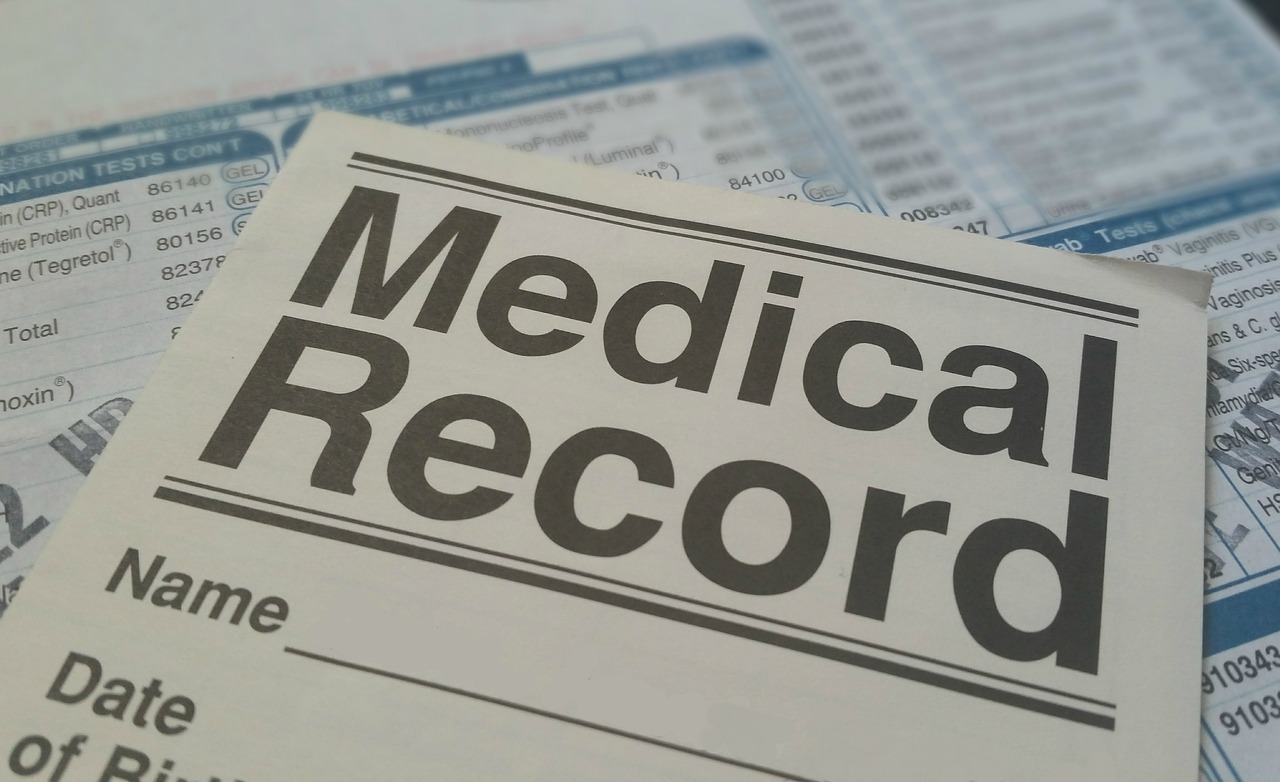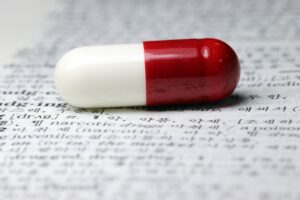病院薬剤師の仕事って、患者さん側からは見えない業務が多いですよね。
これから薬剤師を目指そうと考えている学生や、転職を検討している方からすると、不明な部分が多いように思うかもしれません。
この記事では、私が経験した病院薬剤師としての仕事ややりがい、そして医療業界の今後の方向性について紹介しています。

病院薬剤師の仕事は?
病院薬剤師の仕事内容
病院薬剤師の仕事には、病院内での調剤業務や監査、調剤薬局での患者指導など様々な業務があります。
私が勤務していた地方の病院には薬剤師が30人程いましたが、薬剤師はずっと薬剤部内にいるわけではありません。
例えば、
- 注射室での注射剤を処方箋毎に取り揃えて病棟に払い出す作業
- 医師や看護師からの問い合わせ受けて、その対応に追われる業務
- 抗がん剤や中心静脈栄養など、感染リスクや自らへの被曝を避ける為、特殊な閉鎖空間や無菌の部屋での作業
- 看護師などへの薬剤の取り扱い勉強会
- 各々の所属する委員会の会議や勉強会に参加する
- 病棟での患者教育
これら以外にも様々な雑務があり、割り当てられた業務を着実にこなしていきます。
病院薬剤師のやりがいとは?
調剤室にいる薬剤師は、患者さん個々の病態を把握しようとしても、カルテから得られる情報しかわかりません。
担当薬剤師は患者の病歴、副作用歴、検査値などの情報だけでなく、担当の患者の経過を継続的に把握しています。
一見、問題なさそうな処方であったとしても、担当薬剤師はより患者に適した薬剤の使い方を知っているかもしれません。
医師が患者さんに合わせた最良の治療を行っていると思うかもしれませんが、医師も人間ですので迷うこともあります。
薬のエキスパートとしてダブルチェックの機能を果たすのが病院薬剤師の役割です。
私が懸念点を医師に提案したことで、
 看護師
看護師主治医の治療方針が変わり、未然に患者さんの病態悪化を防げましたよ!
めったにあることではありませんが、そういった経験したこともあります。
入院中の患者から質問をされ、真摯に対応することで感謝の言葉をいただくこともあります。
病院薬剤師として仕事をしていると、やりがいを感じる機会が多くあります。
病院薬剤師とカルテとの関係
紙カルテと電子カルテについて
病院薬剤師の業務を語る上で、カルテの存在は欠かせません。
私が勤めていた病院では10年前まで紙カルテを扱っていました。
紙カルテとは、その患者さんのデータや検査値の結果、医師の指示、その他諸々全てが紙に記録されているものです。
当時は、この紙媒体のカルテこそが薬剤師泣かせの存在だったのです…
例えば、電子カルテであればどの端末からでも、簡単にカルテ情報を閲覧できますが、紙カルテではそうはいきません。
まず、紙カルテを確認するためには、患者のいるフロアのナースステーションに確認しに行かなければなりません。
また、その患者が検査などで不在の場合は、紙カルテも患者さんと一緒に移動しているので、ナースステーションにありません。担当医が指示を書くためにカルテを手元においている可能性もあります。
そうなると、いつカルテが戻ってくるかもわかりません。
紙カルテがナースステーションにあったとしても、看護師が患者の記録を書いていれば、書き終わるまでは看護師の邪魔にならぬよう、相手の顔色を伺いながら待たなければなりません。
当時の病院では、看護師と薬剤師は犬猿の仲だったので、とても気楽に聞けるような雰囲気ではありませんでした。
このように、たった1人のカルテを確認するためでも、紙カルテだと沢山の障壁が存在していました。
電子カルテになって良かったこと
紙カルテには患者の病歴、検査値、定期薬、バイタル、担当医の指示など、様々な内容が綴られています。
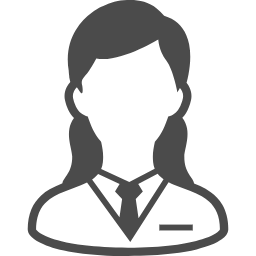
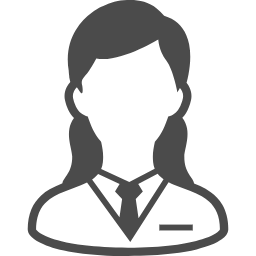
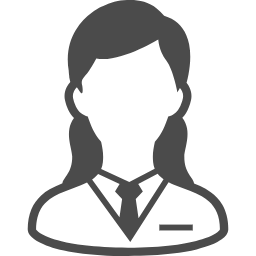
雑で汚い、象形文字のような字を読み解くのも一苦労…
もちろん、検査値は電子カルテのようにグラフ化されていません。
検査結果が出るたびに新たに結果が綴られているだけです。以前の検査結果と見比べて1つずつ検査値を確認しなければなりません。
さらに、紙カルテが嵩張り、ファイルが外れてしまい、ナースステーションにバラまいてしまったこともありました。



当時の事を思い出しながらこの記事を書いていますが、本当にこの時代は大変でした…
【超絶激務】紙から電子へのカルテ移行作業
便利な電カルを手に入れるためには、膨大な紙カルテの情報をデータ移行しなくてはなりません。
データベースの移行は電カルの会社が概ね行いますが、それだけではダメです。
薬剤師が一つずつチェックし、電子カルテへの移行準備を進める必要があります。これらを本来業務と並行して行わなければならないのですが、これが地獄の始まりでした…
例えば、数千種類もある採用医薬品の禁忌薬や併用注意などのチェックが設定されているかを添付文書と照らし合わせる作業があります。
患者さんの直近数年の紙カルテの内容と電カルデータに相違がないかを確認します。
具体的には、
- 副作用情報
- アレルギー等の既往歴
- 患者独自の調剤方法(一包化、印字方法、薬袋のこだわり)
データが電子カルテに反映されているか一つずつ確認するのですが、数カ月かけて各薬剤師にノルマが割り振られ、それらを業務時間外に進めていきます。
残業時間で対応するよう指示がきていましたし、昼休憩さえも取れない日々が続きました。今では考えられないかもしれませんが、残業代も手当てもありません。
毎日毎日、みんなでクタクタになりながらの作業をこなしていました。
その後、データ移行が終わり仮運用期間が設けられ、電カル内でデータがそれぞれの部署に正しく指示が飛ぶかを確認しなければなりません。
実際に運用を開始した後も、最初のうちは紙カルテと電子カルテを照らし合わせる作業が続き、様々なアクシデントも発生しました。
このように医療情報の根幹であるカルテの変更には、その業務に携わる医療従事者にかなりの負担が強いられます。
薬剤師業務に大きな影響を与えたカルテの電子化
今となっては電子カルテの画面をポチッと押せば簡単に添付文書やインタビューフォームを見れるのが当たり前の時代となりましたが、10年前はアナログの時代でした。
添付文書は箱にまとめてあり、内服、外用、注射剤の採用薬剤全てを五十音順にファイルに閉じていました。
さらに、添付文書は随時更新されるので、少なくとも1年に1回は何キロもありそうなファイルの中身を全て入れ替えるという作業を行っていたものです。



今ではとても考えられないですよね…
電子化により、病院薬剤師の業務が大きく変わった瞬間でした。
カルテの電子化で得られたメリット



患者の○○さん、最近吐き気があるみたいなんだけど、今飲んでる薬で吐き気の副作用ある?
医師からの問い合わせあるあるです。
そうすると、まずはその患者さんの服用中の薬剤チェックをします。
そして、患者が使用している薬剤の添付文書をファイルから探し当て、患者が「吐き気」と感じるであろう副作用(胃不快感、悪心、吐気、嘔吐、消化不良など)の発現頻度を全部網羅して確認します。
これも、今となってはPCでサクッと検索して報告できることですが、当時はとてつもない労力と時間を費やして行っていたものです。
また、処方箋への対応についても大変でした。
まず、看護師が紙カルテに書かれた象形文字のような字を一つも間違えぬように読み解き、手書きの複写処方箋に、生年月日、性別、病室などの必要事項を持ってきます。
薬剤師は各フロアから届く手書き処方箋を元に、薬剤を取り揃え、処方箋の指示と相違がないかをダブルチェックで確認し、それらを各フロアに届けるのです。
手書き処方箋には検査値や既往歴などは書いていないので、その患者の肝機能や腎機能、禁忌の病歴や他に服用している薬などは知りようがありません。
ひたすらに手書き処方箋を元に用法用量を間違える事なく、より確実によりスピーディーに処方箋をさばく必要がありました。
しかしどれだけ気を付けていても伝達ミスは必ず起きるので、



電子化でヒューマンエラーが起きにくくなっているのでは?
と思います。
ここに関しては、今後いろいろな電子化によるメリットや効果を検証したデータが出てくることが期待されます。
電子カルテでは、医師が指示を登録したと同時にそれぞれの部署にオーダーがとんできます。
- 薬剤部には注射や内服の指示
- 検査部には採血やレントゲンなどの指示
- リハビリ部には患者の状態に合わせたリハビリの指示
- 管理栄養士にはカロリーや塩分制限、食べてはいけない食材などの指示
このように、あらゆる指示がPCで入力するだけで関係各所にデータとして伝達され、各々の部署で実行されてきます。
薬剤部でも、担当に関わらず処方箋で調剤する前に必ず患者の状態を確認できるため、より安全な医療が提供出来るようになったと実感しています。
テクノロジーによる医療業界の将来性
2024年には、紙の保険証を廃止しマイナンバーカードへの統合等が国策として進められていますが、私は基本的な方向性として賛成です。
これにより、様々な医療機関にかかっている患者の情報が連携されていくことで、残薬調整による医療費の抑制や個別化医療の推進などのメリットが期待されています。
しかし、これも患者情報を扱うという、絶対に間違えてはいけない領域での大きな変化ということを忘れてはなりません。
今後は、電子処方箋や遠隔診療等の普及など、医療業界にテクノロジーが組み込まれていくので、医療従事者の仕事も根本から変わることが想定されます。
最近では、AIを用いた画像診断や、ダヴィンチによるロボット手術、遠隔診療、ドローン配送なども増えてきています。
うまく利用すれば劇的に利便性の向上が期待できるので、薬剤師の仕事も大きく変化するかもしれません。
クリニックの門前薬局で、ただ薬を渡すだけのような仕事は淘汰されていくことでしょう。
薬剤師は、患者個々の病態に寄り添った薬剤の適正使用を推進するために、患者とのコミュニケーションをいかにとっていくかが重要になってくると考えています。
今後も、薬剤師として経験してきたことを情報発信していきますので、引き続き応援よろしくお願いします。